学校のテスト順位から北辰偏差値を予想する

近隣の富士中の1学年の生徒数が250人くらいなのだけれど、定期テストの得点分布と北辰テストの成績分布が結構似ている形をしている。
だから、学校の順位を見れば北辰テストを受けたときの成績もざっくりと見えてくる。もちろん全く同じものではないので話半分に聞いてもらいたいのだが、4月の北辰テストを受けられない子もいるので、受験勉強をするときの自分の立ち位置を知る参考にしてもらえれば幸いだ。
【学校の定期テストの順位】【北辰テストの偏差値】の順
6位以上 70以上
23位以上 65以上
57位以上 60以上
101位以上 55以上
148位以上 50以上
195位以上 45以上
228位以上 40以上
244位以上 35以上
なお北辰の成績分布は、2023年度3年第6回を参考にした。
学校の定期テストは短距離走な側面もあるので、今回だけブーストかけて順位が良かったからと言ってこの偏差値を取れるわけではない。そもそも偏差値ってその時の受験者によって変わるものだからね。あくまで予想の範疇を出ない。でもウチの生徒の成績で照らし合わせてみると結構イイ線いってるんじゃないかしら。大事なのはここからどこまで伸びるかだからね。
苦手科目には

不得意科目をどうにかしたい場合は、その科目を好きになるのが近道だ。
とはいえ、不得意科目というのは「嫌い」という気持ちとセットだ。不得意だから嫌い。嫌いだから不得意。そりゃできないものはそうなる。だから、嘘でもいいので「好き」と思いこむことがひとつの突破口になったりする。なんだか人間関係の話みたいだね。
でも人間関係と違うのは、相手は常に自分のことが「大好き」だということ。どんなに嫌でも毎週会うことになるし、定期テストの日には必ず待ち合わせる。ほらね、自分のこと大好きじゃん?
だから少しだけでもいいので、「まあ、本当に嫌いにはなれないよな」くらいに思って相手をしてあげよう。もしかしたらその科目も、意外と良い一面を持っていたりするかも知れないよ。
「そそっかしい」ではなく「力が足りない」

新中学1年生に英語の問題を解いてもらった。中1向けの長文読解だ。
分からない単語は自分で辞書を引くことを徹底してもらう。こうして自分で調べる習慣があるのと無いのとでは後々の成長が大きく変わる。自分で自分を伸ばせる子になってもらうためにも、まずは自分で動く習慣からだね。
それできちんと知らべて和訳も良くできているのだけれど、問題を解く時のミスがまだ多い。並べ替え問題なのに全文を空欄に入れてしまう、日本語で答える問題なのに英語で書いてしまう。こういうのは中学校のテストではバツだ。今までは指摘するだけだったけれど、今日からはハッキリと「×」印を付けた。
こういう「分かっていてもバツになる」ミスを、単に「そそっかしい」で片づけてしまってはいけない。学校のトップ層はこんな間違いしないからね。自分のミスに自覚的になるように意識付けしていかなくてはいけない。1問1問を大切にして、1点を取るために全力になれる子になってほしいと思う。
今日は暑い

なんか夕方になって暑いなー暑いなーと思っていたら、外は25℃もあると生徒が教えてくれた。そりゃ暑いわ。
もくせい塾は建物の最上階にあるせいか、日が当たっていると簡単に室内の温度が上がる。外よりも暑くなってしまう。それで今は窓を開けて放熱をしているのだけれど、
「これはエアコンをつけることも視野にいれねば」
というカンジだ。
でも昨日まで夜に暖房をつけていたのに、今日いきなり冷房とか。なんだか倫理的に「いいのか?」って思ってしまう。エアコンに頼らない時期が1ヵ月くらいはあるもんでしょ、ってね。昭和の人間なもんで。もちろん生徒の体調以上に大切なものはないのでね。その時が来たらためらっている場合ではないのだ。
英検のリニューアル

英検の問題が変わるらしい。
具体的には、ライティングの問題が1題から2題に増える級が増えるみたい。ライティング、英作文の比重が増える。その目的は、「新たな英語能力観を反映した出題形式を取り入れ」ということらしい。
今まで、例えば3級ならば中学卒業程度の内容なんて言われてきたけれど、「早期取得」競技みたいになっていた。「小学生で3級を取りました!」みたいな。売ってる問題集を真面目にやれば未習分野があっても取れちゃうからね。でもそれゆえ、英検を持っているのと英語の力があるのはまた別な気もしていた。今回のリニューアルでより正確な英語能力の測定になればいいなと思う。進学の資料に対してもまた見直されるようになるかも知れないしね。
長期休みになると変化する生徒の行動

春休みだ。
こういう長期休みに入ると生徒の行動に変化が表れることがある。休みだから自習に来なくなっちゃう子とかもいる。
確かに遊びたいという気持ちは分からなくはない。こういう子が休み明けに、小鹿のようにプルプルとした字をシャーペンで書いているのを見て
「がんばれー!がんばれー!」
と、応援するのも仕事だ。でも、長期休みになって反対に自習量が増える子もいるんだよね。こういう子はいわずもがな、学校の課題をさっさと終わらせて自分のやりたかった勉強に取り組んでいる。自分の持っている時間というものに自覚的だからできるんだよね。そういう子には、
「頑張って!」
と、より深い勉強の仕方を教えたり、取り組んでいる問題の解説をしたりしている。
この両者が休み明けに学校で同じ教室にいるの、ちょっと信じられないよね。生徒にはどっちの応援を受けたいか、それを一度考えてみてほしいな。どっちも平等に応援はしている。
姿勢は整えるべき?

生徒と読んだ文章読解の文に、東洋と西洋の教育と姿勢についての話があった。(「日本人は何を考えてきたのか」齋藤孝著)
東洋では、「体を整えることによって精神を整える」とういう伝統があるため、身体と言葉と精神が一体化した教育が行われてきた。よって教育を受けるときの姿勢も重視される。
一方西洋では、古代ギリシャ人のように寝っ転がったりお風呂に入ったりしながら議論していたことからも、知的に高度であることと姿勢を整えて礼儀正しくすることは直結していない。
確かになぁ。では現代の学校や塾での授業風景はどうあるべきなんだろうね。ちなみに私が中学生の時に通っていた塾では、講義中にちらっとよそ見でもするものなら、
「おいテメェー!どこ見てんだよオラァー!」
と、ヤンキーバリバリ語でその姿勢をどやされたものだ。(ん?これ東洋西洋どっちだ??)もちろん頬杖なんて絶対にNGだ。
ある程度は厳しかったけれど、東洋的学習姿勢の効果も確かに実感していた。問題を解くときやノートを書くときって、姿勢の正しいほうが絶対に速いんだよね。首を動かさずに目だけで問題文を追えるしミスも減る。腰痛にもならない。先生の話を聞くときも鉛筆を持たず手を膝の上に置いて先生の目を見て聞くことで、余計なものに気を取られないから話が入ってきやすく身に付きやすい。
やっぱり勉強という型を教えるには姿勢も正したほうがいい効果は生まれるのかも知れない。そうした型が身に付いた上で知的生産をしていくには、西洋のようなリラックスも必要なのだろうね。
算数はスーパーへ行け

小5の子たちの算数も一通り学習が終わり総復習に入っている。
5年生くらいから算数は難しくなる。抽象的な概念が入ってくるのと、あと「割合」ね。こみぐあいにはじまり百分率・歩合、割増し・割引、速さもそう。こうした単位あたりの量に強くなるには、「日常生活」がポイントだと思う。
スーパーなどに買い物に行くと、そこは割合を勉強する宝庫だ。割引シールもそうだし、お菓子の「〇パーセント増量中」の文言。あと「1gあたり〇円」となっている調味料の値札もある。衣料品店もいい。割引された値札を見ていくらで買えるか。これらを実際に計算してみるとあっという間に割合はできるようになる。保護者の方は是非試してみてほしい。
自分のことを思い出してみても、こうした割引シールが教材だったような気がする(値引きされたものばかりを見ていた悲しさはとりあえず置いておいて)。子供の学力には机で勉強させることも大切だけれど、おつかいをさせるのも同じくらい効果的な気がする。
北辰テストの解き直し

中2で、北辰テストが返却されて自習で解き直しをしている生徒がいた。良い感じだね。
北辰テストの解き直しは、返却された成績表の「正答率」の高い順にやっていくのがいい。自分が間違った問題を解き直して、それに関連する勉強を教科書や問題集に戻って行うと効果的だろう。今は確実にできる問題を増やしていくことい意識を向けていくべきだ。
ちなみに、学校選択問題採用校を狙っている子には、数学の正答率1桁以下の問題も、しっかり解説を見て解き方をなぞっておいてもらいたい。ここから受験までの間で、いわゆる難問に出会える頻度ってそれほど多くない。北辰テスト自体あと8回しかないからね。せっかく出会えたものなので、今から自分の糧にしていってほしい。その姿勢が上位難関校へ合格するためには必要だ。
新しいテキストを受け取って

発注していた新年度のテキストが届いたので生徒に渡し始めている。
やっぱり新しいものはテンションが上がるよね。受け取った生徒たちもちょっと嬉しそうだ。これでたくさん勉強することになるのにね。
新学年のテキストが渡った生徒はすぐにでも次の学年の内容を進めていける。解説授業とか、その仕組みはもうあるからね。最低限のペースメイクはしていくけれど、生徒の意志次第でいくらでも先の勉強ができるのがもくせい塾のカリキュラムだ。今年はバリバリに早く進んでいくような子は出てくるだろうか。ちょっと楽しみだ。
元塾生が来た!

昨日、授業が全て終わって生徒を送り出して少ししてから、コンコンとドアをノックする音が。元塾生が遊びに来てくれた。
大学を卒業したとのことで挨拶に寄ってくれたとのこと。ありがたいですね~。
大学の話、留学に行った話、就職の話、いろいろ聞かせてもらった。
「ずいぶん立派になって」
なんて親戚のおじさんみたいな感想を持っちゃったよ。
結構長い時間引き留めてしまって申し訳ない。嬉しくてついね。こうして塾を離れてからも頑張っているのを教えてもらえるのは望外の喜びだ。この仕事をしていて一番かも知れん。これからも仕事の息抜きに遊びにおいで。
記述が書けない?書かない?

最近のもくせい塾ではほとんど見ないけれど、「記述問題を『白紙』で出す子」というのがいる。
保護者の方にこのことで
「ウチの子、記述問題が苦手なんです」
と相談されたこともあったけれど、ハッキリ言ってこれは記述が得意・不得意という段階ですらない。
記述が苦手というのは、書いても書いても得点にならないということ。これなら具体的に対策もできる。聞かれたことに対して適切に本文から根拠を見つけ出せているか、それを問われた形で答えられているか。そのチェックをして修正していけば得点につながる。結局記述問題であっても記号問題と考え方は同じだからね。
書いてすらいないのでは、そもそもマウンドに立っていない。毎回記述問題を空欄にしてしまう子、きっとその根底には「面倒臭い」が横たわっている。そしておそらく、それを許してしまった環境がある。日本で教育を受けている子はたぶん全員こう言われてきているはずだ。
「なんでもいいからとりあえず書いてみよう」
それをしなかった段階で問題に取り組むことを放棄している。そしてそうなった時すぐに修正されずに放置されてしまったのだ。それを「許し」と感じて現在まで続いてしまっている。きっとこんな感じなのだろう。かわいそうだよね。これは、学力ではなく姿勢の問題なのにね。
学力的にどうしても書けない、というところまで陥ってしまっているのなら、記述問題ではなく記号問題からさせるべきだ。読んで書けば正解できる。まずはその姿勢を取り戻さなくてはいけない。
授業では立ち止まれない

集団授業形式だと、どうしても生徒の意識が逸れてしまう瞬間がある。授業をしている講師も、それが見えてもいちいち授業を止めて注意してはいられない。生徒にも波があるし、学力層によってもまちまちだ。全員をずっと引き付けられ続けるほどの授業を毎回できるようなスーパー講師じゃないとこれは難しい問題だろう。
なのでもくせい塾の授業は、できたら私の元に持ってきて丸付け確認、分からなければ質問に来る、というスタイルでやっている。
こうすることで基本的に生徒が「止まっている」ことはない。問題演習で頭を動かしているか、私に質問されて頭を動かしているか、私の解説を聞いているか。ボケっとしている子がいたら、すぐに私に捕まる。授業中はずっと走り続けているイメージだ。
答えにくい質問

面談で保護者の方と話すと
「どのくらいいけますか?」
というような質問をされることがある。今の成績だとどのあたりの学校を目指せますか、とか、このままいけばどのくらいまで成績が上がりますか、とか。
これはうかつなことは言えないのでとても緊張する。生徒の伸びを限定することは言いたくない。塾長と言う立場上ある程度の説得力が出ちゃうかも知れないので、ひかえめに言ったりして「呪い」をかけることはできない。しかし、
「いくらでもいけますよ。本人の努力次第でね!」
というのは質問に答えていない気がする。生徒が受験生の場合、残り時間を加味すると本当にどこへでもいけるというわけでもなくなってくる。
しかし、しかしだ。ほぼ毎年、私の予想をはるかに超える結果を出す子が出てくる。私はできるだけ情報を元に判断しているつもりだけれど、そんなのは全くアテにならない。1年で偏差値14アップとか、通知表8アップとか。言われても信じられないよね。
それを実際に見てしまっている以上、「いくらでも~」が実は一番正解に近い答えなんじゃないかとも思える。そんなわけでこう質問されると、曖昧な笑顔を作りながら「えへへ」って言っている(ダメじゃん)。
始めての読書体験は与えるもの

高校生と話をしていて、国語の話になったので本を貸し出してみた。もくせい塾の本棚には文庫本がある。
「ウチの子、本を買っても読まないんです」
とおっしゃる保護者の方が多い。どこも苦労されているのね。だけどそうなるのも当然だ。今はスマホがあるのだもの。
子供に本を読ませるには、本にはそれだけの「価値がある」ということも与えなくてはならない。まず自分の読書している姿を見せているかだよね。それなくてして「本を読みなさい」って言っても「なんで?」ってなっちゃう。「本っていうのはね、勉強になるの」なんて言っても読まんよね。
本を与える自分が読書をして、そこから得た知識を楽しんでいるか。こういう姿を見ている子は「自分も読みたい」ってなる。子供は楽しいことが大好きだからね。
分詞と関係代名詞の問題

中学生が分詞の修飾と関係代名詞の学習を進めるとこんな問題に出会う。
【次の文と同じ意味になる文を分詞を用いて書きなさい】
The man who is cooking in the kitchen is my father.
答えは
The man cooking in the kitchen is my father.
なのだけれど、こう間違える子がいる。
My father is cooking in the kitchen.
んー、丸にしてあげたい。文法的にも何も間違っていない。設問の条件も満たしている。問題は「台所で料理をしている男性は私の父です」なので、日本語で「私の父は台所で料理をしています」だとちょっと違うんだけどね。言いたい情報は伝わると思う。
これは問題としてはバツだけれど、日本語にして考えられてはいるんだよね。そういう意味では結構高度なことができていると思う。
平等にあるから怖い

時間は誰に対しても平等だ。1日24時間。
言われれば当たり前過ぎて反対に誰も言わないくらいだけれど、これに気付いた時「怖い」と感じた。確か中学生の時だったと思う。
誰にでも同じ時間が与えられているのならば、同い年の人の差ってどこからくるんだろう。もちろん才能のようなものの違いだってあるだろうし、生まれた環境の違いだってある。でも時間をかければ伸ばせる能力の差は何が原因だ?みたいなことを考えた。
もちろんそんな思いはすぐに霧散して、ちゃらんぽらんな学生生活に戻っていったので何か大成することは無かった。けれど時間を無駄に過ごしたときの罪悪感のようなものはその時から強くなった気がする。
体の使い方

小学生の頃、自分のことを運動音痴だと思っていた。でも中学生になり運動部に所属すると、
「それは違うのかも知れない」
と思うようになった。
別に部活動で目覚ましい成績を修めたわけでもないし、スポーツ面で活躍できたわけでもない。そう思ったのは、部活動の練習の時に「体の使い方」のようなものを学んだのがキッカケだったような気がする。ラケットを「こう振る」と、球が「こう飛んでいく」、みたいな。運動にも学習の段階があって、反復練習してモノにすると技術が向上して上手くなるのだ、と気付けたのは高校生くらいになってからだと思う。その時には積み上げの量に大きな差がついていて、すでに自分は「運動の人ではない」と思っていたけれど。
勉強も運動も結局同じことなんだと思うようになったのは大人になってから。今は「体の使い方」を練習することなんだろうなと思っている。運動でも勉強でも、それに必要な体の部位の使い方を練習する作業ってことね。
だから偏差値の高い学校でスポーツも盛んって所が多いのもうなづけるし、プロスポーツ選手が話す時はとても理路整然としているなぁと感じる。このことに小学校の頃に気付けていたならば、もう少し部活動でも活躍できたかな、なんて思ったり。
過去分詞との長い付き合い

中2の英語は中3の学習内容に入っている。
まず出てくるのが現在完了進行形。これは直前でやった現在完了形の続きなので、まとめて勉強だ。それが終わると受動態。そして分詞の修飾の学習に入る。もうここを通り過ぎた子もいる。
ここまでの文法に共通するのは、全てに過去分詞が使われるということ。ということは、不規則変化動詞の活用の暗記を避けて通ることができないのだ。せっかく文法の形が分かっても単語が書けないとテストで間違えになっちゃうからね。過去分詞とはこれからも長い付き合いになるよ。
なのでこの春休みを使って動詞の活用表をしっかり復習しておこう。動詞の発音の仕方は、中2英語のフォルダ内に動画あるので見ておいてほしい。読めなきゃ書けない。書けなきゃ点が取れない。
no more 「writed]、no more「maked」。
本を読まずに読書量を増やすコツ
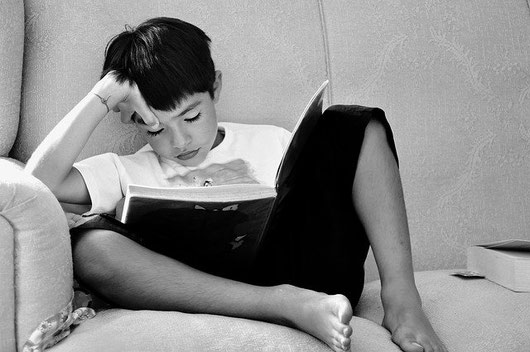
小学6年生たちは、国語で中学生の問題集を使っている。
短めの読解問題集なのだけれど、太宰治や芥川龍之介の文章なども載っている。少し背伸びした文章に触れるには良い教材だと思う。本で「太宰治を読め~!」と言ってもなかなか通らないけれど、問題集に入っているものは嬉々として読むのが面白い。国語に学年は関係ないからね。やや難しい言葉も出てくるので、脳に新鮮な刺激が加わるはずだ。
現在、その問題集もほぼ終わりに近づいてきている。小学生用のワークももちろん終わらせてあるので、これで2冊目。ずいぶんと文を読む力は付いてきた。やはり読書量を稼いでおくことがこの時期の生徒には必要だ。国語は全ての勉強の基礎なので、早目に育てておくほうが絶対にいい。
ハードルを並べるお仕事

塾講師として駆け出しの時期を過ぎた頃、自分の「指導技術」みたいなものを伸ばしたいと思うようになった。
どうすればもっと分かりやすく教えられるのか。もっと上手くなりたい。そう思って腕を磨こうとしていった。すると不思議なことに、教えている生徒の学力はだんだん伸びなくなっていった。
どうやら教えすぎていたらしい。生徒が躓きそうなところを「先回りして」小石を取り除き、躓かないように、歩きやすいように舗装する作業ばかりしてしまっていた。今なら分かるけれど、生徒を「できるようにさせる」ことと、「楽をさせる」ことは全くの別物だ。
だから今は、生徒に負荷をかけることを意識している。余計な小石は取り除くけれど、その上でハードルを並べて飛んでもらうようにする。生徒の足腰を鍛えることが、本当の指導技術なんじゃないかと思うようになった。
すぐに眠くなってしまう

面談で保護者の方と、
「最近になって、子供がすぐに寝てしまう」
という話になった。結構あるあるだ。
すぐに寝てしまう、いわゆる寝落ちしてしまうにはいくつか原因があると思う。例えば疲れているとか、睡眠が足りていないとか、春だから(?)とか。私は専門家でないので詳しいことは全く分からないけれど。
あと中学生くらいだと「成長期だから」というのもあるかも知れない。私も中学生くらいの時にあったような気がする。寝ても寝ても眠い時期。体を作るのにエネルギーを使うのかな。
元々睡眠時間は短いほうだったけれど、この時期はまず起きていられなくなった。だから学校から帰ってきてご飯を食べたら30分寝て、起きて塾に行くみたいなことをしていた。眠い時は頑張ってもどうしようもないんだよね。
勉強ができるようになるには

勉強が進んでいくと、どんどん身に付けるべき事柄が増えていく。
だからそれが抜けてしまうこともある。人は忘れるものだからね。そうなった場合、それを復習して身に付け直す必要が出てくる。何度も、何度でも。
忘れてしまうのは、脳が「必要のない知識だ」と判断した時に起こる。だから勉強の内容に興味のある子は忘れにくく、興味の無い子は忘れやすい。しかしそれを何度も反復していくとだんだん忘れにくくなっていく。繰り返し見たものは重要度が上がるらしいのだ。
そしてそれを続けるうちに、勉強自体が「重要なもの」として認識され、一度学んだことをすぐに覚えたり忘れにくくなったりするようになっていく。「勉強ができるようになるにはどうしたらいいですか」の答えは、「繰り返すこと」だろうね。
意味がある宿題ならば

もくせい塾では、基本的に小学生以外には宿題を出さない。全部じゃないけれど、宿題は効果のほどがあまり信用できないと思っているからだ。
自宅でやってきてもらうので、宿題の確認をするときには、すでに「終わった」作業の確認となる。だから身が入らずに雑にやっていたとしても、それを知るのは「終わった」後なのだ。雑にやったせいでできていないところがあったとしてそれをもう一度やらせるくらいならば、はじめから私の目の前でやってもらうほうがいい。
もちろんきちんとやる・やらないはその生徒次第なので、やらなくても出すという選択肢もあるけれど、出して「出したからね。あとは君次第だよ」と自己責任にしてしまうのもちょっと嫌だよね。
だから勉強は塾で完結して、家は憩いの場にしてもらうことが理想だ。
しかし、「宿題ください」と生徒本人から言われれば喜んで出す。その場合はきちんとやってくるはずなので、出した宿題も効果的なものになるはずだ。
100点ってどう取るの?

学校の定期テストであっても満点を取るのは難しい。自慢じゃないけど、私は学生時代に1度も取ったことが無い。
99点ならある。でも100点は無い。それ以来感じているのは、
「99点と100点の差は『1点』よりもずっと大きい」
ということだ。100点を取るには1つもミスをしてはならない。まずテスト範囲の内容が100点に到達するだけ身に付いていて、その上で慎重に慎重を重ねてテスト時間内に問題を解き切らなければならない。自分もやっていたつもりだけれどついには及ばなかった。
思い返してみて、99点を取った時に私は点数に「喜んでいた」はずだ。もしかしたら、ここで悔しがれなくては100点は取れないんじゃないだろうか。もくせい塾にも過去100点の答案を持って来てくれた子はたくさんいるけれど、そういう子たちを見ていてそう思うんだよね。
本気でやれるように出さなくてはいけない

今日小学生の宿題の丸付けをしていたら、ある生徒の答案がバツのオンパレードだった。
正解できる力は十分にある。そのミステイクは意識からくるものだ。文字がミミズなのですぐに分かる。そこで、
「字が死にそうだけれど、宿題やっている時にゾンビタイムあった?」
と聞くと、
「ありました」
との答えが。うん、素直でいいね。しかし、勉強を「抜いて」やると癖になる。いつでも全速力が出せるようにしておかないと、本人は無意識でも楽する方向に流れていってしまいかねない。ここが宿題の難しいところだと思う。宿題を出すことが、逆に生徒の伸びる力を奪うことにならないように気を付けなくてはならない。
ものすごい風

昼までは晴れていたのだけれど、夕方から急に雨になり、雨がやんだ今は強風が吹いている。外を歩く人も少ないみたい。普段は聞こえる外の話し声も今日は全くない。
秋もだけれど、春の天気は本当に変わりやすい。
小学生の授業の時に生徒から「塾に来るときいきなり雨になった」という話題になってそんなことを思った。車で送り迎えしてもらったそうなので大丈夫だったとのこと。
自習に来た子にも
「風とか大丈夫だった?」
と聞いたら、「車で送ってもらった」とのこと。なるほど。ならば安心だ。あとは自転車で来てしまった自分の身を案ずるだけとなったようだ。夜にはおさまるかな。
春分の日

今日は春分の日で祝日なのね。学校帰りの生徒の声が聞こえないのでなにか違和感を感じていたけど、先ほどようやく分かった。
春分の日ということは、昼と夜の長さが同じ日かぁと思ったのだけど、
「本当にそうなのかな?」
と思って調べてみたら、どうやらそれは間違いのようだ。
確かに春分・秋分の日の太陽は真東から登り真西に沈むので、軌道の長さでいうと昼夜半々だけれど、
- 太陽に大きさがあるため、「日が差し始める時間」は太陽の中心が地平線を出るより前から始まる。
- 日の入りも同様。太陽の中心が地平線の下に沈んでもしばらくは日が差し続ける。
- 地球に大気があり光が屈折する。それで遠くの物体が実際より高く見えるのでもっと早くから明るくなる。
ということで、時間でいうと16分ほど昼のほうが長いらしい。へー。
勉強になった。中学生に天体の授業をするときに、「春分の日は昼と夜の『時間』は同じ長さ」と言ってしまっていたかも知れない。修正しなくてはいけないね。楽しい。
間違ってるのは自分の答えか常識か

自分の解答が「常識的に」どうかを判断してほしい。
方程式の文章問題で、電車が2分で通過するトンネルの長さを求める問題があった。生徒が解いてきた答えが
「4m」
...いやいや。それ電車に乗る必要ある?2分で4メートルしか進まない電車なんて嫌だよ。
それで解き直ししてもらったのだが、次に持ってきた答えが、
「43800m」
...いやいやいや。43キロを2分で走る電車なんて乗ったら大けがしちゃうよ。時速1290kmの乗り物。ジャンボジェットより速いのが地上を走ってたら怖いよ。
問題を解いたら、自分の常識と照らし合わせてほしい。
確率で苦手克服!?

中2の子が数学で確率の勉強をやっているのを見ていて思った。
「これ、『数学嫌い』を克服するのにいいかも」
確率は数学の中でもかなり具体的な事象を扱う分野だ。関数のように「変数xが~」なんてことはなく、「結局いくつやねん」と聞いてくる。だから実際に手を動かすと解決することも多い。
また、公式や定理なども少ない。「(求める数)÷(全体の数)」だけでいい。図形問題のようにあれもこれもと定理や公式を覚えなくてもいいのは数学嫌いにとって負担が少ないのではないか。
もちろん問題を読む国語的な力が必要になってくるのだけれど、「書けば分かる」というのは数学が分からない子にとっては都合がいい。実際に、他の分野ではあまり自信の無さそうな子でも、一心不乱に紙に樹系図を書いている。
だから「数学が苦手で苦手で...」というザ・文系な子は確率の勉強から始めてみるといいかも知れない。
長文を読んで文法の確認をする

高校受験生・高校生と英語長文を読むときは、中に出てくる単熟語だけでなく、文法事項や構文も生徒に確認しまくる。それはもう暴風雨のように質問を浴びせかけ答えさせる。
高校生になると、中学生の英文法がしっかり身に付いていないと英語の学習がキツくなる。中学生の時に「なんとなく読み」で凌いできてしまった子は特に。そうすると、高校の英語で「何が間違っているのかが分からない」ということになっていく。
そうならない為にも、ことあるごとに中学校の文法事項の確認から復習をしていく。英語のそこそこできる高校生でも、中学生時に習ったはずの文法事項にボロボロと穴が見つかることがある。「現在完了は『have+過去分詞』」ということが分かっていても、「じゃあhaveの品詞は?」と聞かれると答えられない子も多い。
だから、そういった基礎事項を長文読解の中で復習していく。文法を1から復習する時間はなかなか取れないのでおススメのやり方だ。これを続けていくと、文法問題演習にも効いてくる。
広告がいっぱいだ

自分の勉強の為にいろいろなブログを見たりするのだけれど、「楽天ブログ」を見ようとすると広告が表示されるようになった。
今まではバナー広告が出たりはしていたけれど、記事を読んだりするのには問題無かった。しかし今回は広告を表示させないとブログの先を読むことができない仕様だ。スマホのゲームアプリみたい。「広告が閉じるまであと5秒」。うーん。結構楽天ブログを使われている人のお気に入りも多いのでこれはなかなか面倒だ。
あと、少し前から「戻る」ボタンを教た時にブログランキングみたいなページに飛ばされるのもちょっとストレス。パソコンで見てるからかな。5秒くらいでサクサク行きたいんだけどなー。
中2第2回北辰テストの数学

中2第2回北辰テストの結果が返却されていて、生徒と結果を見て面談している。
今回、数学の平均点がやけに低いなと感じたので以前のものを調べてみた。以下過去3年分の中2第2回北辰テストの平均点。一番上が今回のもの。
2023年度 国58.9 数37.8 社45.6 理38.0 英43.9
2022年度 国55.9 数42.0 社55.5 理38.0 英41.9
2021年度 国55.3 数41.8 社50.9 理41.0 英43.8
2020年度 国50.9 数48.8 社47.6 理32.0 英44.0
国語はだんだん平均点が上がっており、数学はだんだん下がっていて今回30点台に割り込んだ。理科が低いのは相変わらず。今回は社会も低いけれど、5科目の中では数学が最も低い。へー。たまたまかも知れないけれど、数学が難化しているのかも知れないね。確かに問題は県立入試問題に模してあるので難しい。まだ受験勉強をはじめたばかりの子たちが受けるにしてはなかなかヘビーだ。しかしこれは旨味がたっぷり詰まっているので、しっかり直しをしておこう。
学力向上の兆し

「『5×32』を『32×5』として計算すること」は、その子の学力に革命をもたらす。
ちょっと言い過ぎかも知れない。でも、それまで「5×32」と筆算して桁をミスしていた子が、ある日急に「32×5」と計算するようになる。そのように計算したほうが「間違えない」と気付いて自分のやり方を修正したのだ。これは大きな1歩だ。
自分のやり方を見直してより良いほうへ舵を切るのは、大人でも簡単にできることじゃない。それを勉強に対して行えるのは、自分の勉強を「俯瞰で見る」ことができている証。そうして自分で自分の勉強を見るようになった子の学力はグングン伸びていく。
今日は風が強いので

「桜の花が咲いているな」
と思ったのが3月のはじめくらいだったか。
そのことを投稿しようと思っていたのも束の間、
本日教室に向かっていると、桜の花がすでに散っていた。残念。
時期的なものもあると思うけれど、
今日はかなりの強風が吹いているのも原因だろう。
教室に来るときは十分のお気を付けください。
小学生のうちから高校見学に連れて行く

小学生の保護者の方と面談をしていて、
「高校の説明会に参加した」
ということを聞いた。できる子の親は動き出しが早い。
また大学のことや高校のこと、受験のことなどは全然分からないので情報を集めている最中だとおっしゃっていた。しかし、それでも子供の興味の分野を先に見せてあげようとする行動力はすごい。
比較検討する材料があるほど、それが具体的であるほど選択肢は広がるよね。
上位私立高校の数学は「急がば回れ」

新中3の中には、志望校がなんとなく見えてきて、勉強にグッと身が入り始めた子たちが出て来た。
公立高校第一志望の子も私立高校第一志望の子も、ほとんどが私立高校入試は経験することになると思う。そこでひとつポイントを話しておく。
上位・難関と言われる私立高校の数学入試問題には複雑な計算問題がある。これには計算の「工夫」が求められることが多い。
一見ごちゃごちゃと複雑そうに見える計算問題でも、ひと手間加えると急に簡単に処理できてしまうのだ。そういった問題で高校側は生徒の「工夫力」のようなものを見ようとしてくる。だから問題に対して真っ向勝負を仕掛けてしまうと、それだけで試験時間を食いつぶして後半の問題まで手が回らなくなってしまう。
受験勉強でそういった問題を解くとき、手を付け始める前に、「おやおや、これは...」と一旦問題を見て工夫できないかを考える癖をつけていこう。
自分で説明することが、学力を練り上げる

今週は面談が立て続いた。ご参加くださった保護者のみなさま、お忙しいところありがとうございます。お話いただいた内容は今後の指導に活かしていきます。
ところで、小学生のお母さんから、
「子供が、問題の『説明』をしてくる」
という旨の話をよくいただいた。これはいいね!
授業で取り組んでいるテーマのひとつだ。問題を解いて丸付けしたら、私の元に間違えた問題などの「説明」をしに来させる。どこがどう間違ったのか、なぜその答えになるのか。
自分で解説するのは、その問題を咀嚼して飲み込んでいないとできないことだ。だから私の前で止まってしまわないように自分で解説を見て「理解する」ことが求められる。これが問題演習を栄養にするポイントだ。
また、「解説」には技術がいる。論理だてて説明する技術ね。今は高校入試でも大学入試でも国語的な力が強く求められる。読める・書ける、じゃないとどの科目でも高得点は望めない。だけど多くの子が本を読まなくなっている。これを補うにはこうしたトレーニングが必要になってくる。
だから生徒たちが家でこうした「説明」をやっているのだと聞いて、良い感じになってきたと感じる。おうちの方も面倒かけて申し訳ないが、是非その説明を聞いて、ひとつふたつ質問をしてあげてほしい。子供を伸ばすことにつながるはずだ。
低画質モードってのがあってだね

「先生、タブレットがおかしいです」
と、生徒の子に言われた。教室にある、動画視聴用のタブレットのことだ。
私は
「ありゃりゃ~、ついに壊れちったかな」
と思い、生徒の言っていたタブレットを見に行った。
「ほらこれ、なんかモザイクみたいになる...」
と言われ、生徒の指さす画面を見てみると...低画質モード。
「動画の先のほうを見ようとするとなります」
シークバーを動かしながら言う生徒。うん、そうだね。まだ読み込みが不十分だからね。
ウチはyoutubeをプラットフォームにして動画を作っている。教室には一応光回線をひいてるはずなんだけど、もしかしたらその子の家のwifi環境がとても良いのだろうか。またはウチで使っている安物のタブレットのせいか(こっちの可能性が高い)。
「タブレットの性能の違いが、戦力の決定的差ではないことを...教えてやるっ!」
と、強がってみる。
卒業式!

近隣の中学校では、今日が卒業式だった。
ウチからも今日卒業式の子がいるので、
「ちゃんと卒業しておいで~」
と言っておいた。なんだ「ちゃんと卒業」って。尾崎豊か。
しかし、高校に合格するのも嬉しいことだけれど、生徒がきちんと学校を卒業するのも嬉しいことなのよ。高校に進学したけれど最後まで通えなかった子とかも知っているので。特に保護者の方にはまた格別の想いがあるだろう。一生懸命大切に育て上げたお子さんが学校をご卒業なさるのだ。
生徒たちには、階段を一つ上がったその姿をしっかりと親御さんに見せてあげてほしい。ご卒業おめでとうございます。
やらないことを責めるのは、やらせないことにつながる

子供が親の言うことを聞かなくなったらいよいよヤバいと思ったほうがいい。
いわゆる反抗期ならばまだいい。それは誰にでも訪れるし、いつか過ぎるものだから。まだ、「今は自分の足で歩いてみたいんだろうな」で済むかも知れない。
しかし、何を言われても反抗もせず、でも言った通りにやるわけでもないという状態は本当にマズい。「学習性無気力」の状態だろう。
微弱な電流を流した柵に犬を入れておくとはじめは外に出ようとするが、電流を浴び続けるうちに外に出るのを「諦め」てしまい、電流を流さなくなったのが分かってももう外に出ようとしなくなるらしい。これと似た状態になっているのではないだろうか。何をしても罰を与えられると思ってしまうと、努力しても無駄だと「学んで」しまう。
過去に何人か見たことがある。「どうせやっても無駄だから」という姿勢の子。「やったところでどうせ怒られるし」と、言葉にできる子はまだいいほうで、中には従順に従うのだが全く続かない。目を離すとすぐに止まってしまう子もいた。続けるだけのエネルギーが無くなってしまっていたのだ。そういう子の目は虚ろで、見ていて痛々しいほどだった。
「なんでやらないの?」
と子供に言うのは簡単だ。大人は正解を持っているからね。でもそうやって追い詰め過ぎると、ある日子供は「折れる」。諦めてしまうのだ。子供は大人の正論には絶対に勝てない。それをかざし続けると、子供の目は檻の中の犬のようになっていく。
中2第2回北辰テスト返却

中2第2回の北辰テストが返却された。
今回受けた子たちは、受験を意識する良いキッカケになったんじゃないかな。初めて受けた子も、以前受けたことがある子も、今回の成績が自分の受験勉強のスタートラインだ。それを早く知れたことは大きい。
大切なのは今の成績からどこまで伸ばしていけるかだ。これを機に受験勉強をスタートしよう。まずは成績表の出来ていない問題を、正答率の高い順に確認していくこと。そして教科書を使って「深く」復習すること。さあはじめよう。
確率を上げる

中2の数学は確率の学習に入っている。
近隣の中学校ではこの範囲は3学期期末テストが終わってから入ったりすることも多く、定期テストに組み込まれないまま進んでしまったりする場合もある。
すると何が起こるかというと、「苦手なまま受験を迎える」子が出てきてしまうということだ。埼玉県の県立高校入試に確率は必ず出題されているし、高校数学では統計と確率の分野は大きな比重を持っている。さらに、大人になってからも使う数学って確率くらいなもんなんだよね。なのでここを苦手なままにしていていいわけないよね。ここが苦手だと、世の中の嘘にすぐ騙されちゃう大人になっちゃうぞ~。
生徒たちの学習の様子を見ていると、よくできているなと感じる子と、「あちゃ~」な子がいる。「あちゃ~」な子は文章を読むのが苦手な子だ。確率の問題は具体的な事象を扱うので、問題文の内容を頭の中でイメージできないと考えられない。
「少し苦手だな」と感じる子は、塾の本棚にトランプやサイコロが置いてある。それをいじりながら問題を見てみよう。
この人は、ほんとにひどい物言いだ。

今日、生徒に言い放った言葉がある。
「『家で勉強してます』は信用しない」
んまぁ~なんてひどいこと言うんでしょうね~。
自分でもそう思う。自宅で勉強している子だっているのは知っている。しかし、「家で勉強してます」って塾の先生に言うとはどういうことなのか。それを考えると、どうしても「信用できない」のだ。
上の言葉が出る時のシチュエーションを想像してみてほしい。それが出る前に、どんなことを聞かれているか。きっと「勉強をしているのかどうか」を問われているはずだよね。そして勉強をしているかどうかを聞かれるってことは、「勉強してないんじゃないか」と思われてるわけ。疑っちゃって申し訳ないけどね。
例えば、成績が下がったとか、約束した課題・宿題がこなせていないとか、疑われるにはその元となる事実があるのね。何もないのに疑ったりはしないよ?だから「家で勉強してます」はそもそも意味を成していないわけ。だってやってたらその事実は起こらないんだから。「やってるけど成績が下がった・課題が終わらない」はやってないのと同じだよ。だって塾でやれば成績は上がるし課題は終わるんだから。もしそれでも成績が変わらないんだったら、目の前にいる塾長先生のせいにしちゃえばいいんだよ。
と、言うことで「『家で勉強してます』は信用しない」ことにしてんのよ。そこを「信じるよ!」なんて言って、講師として義務「成績を上げる」を放棄するのは怠慢だと思ってるからこう言ってんだわ。だから君も素直に「家じゃやってません」って白状して自習に来なよ。今までそれで何も変わらなくて、ウチの塾に来たんでしょ?
癖を直す

言葉は悪いが、「逃げ癖」の付いてしまっている子は伸びない。
できるだけサボろうとする。だからすぐに休もうとする。そしてやらないための言い訳をする。ああ、逃げよう逃げようとしているな。
たぶんその方法で「上手くいってしまった」経験があるのだろう。そういう意味ではその子も被害者だ。それまでに関わった先生や塾講師がそれを許してしまっていた罪は重い。
だからもくせい塾はそういうことをした子に取り合うことは無い。もちろん話は聞くけれど、例えば交わした約束を破ったりしてその言い訳を繰り出しても、「それで?それがどうした」というスタンスで接している。そういう子は、ここまで自分の理屈の通らない大人には出会ったことないんじゃないかな。それこそ「辞めたきゃ辞めな」というつもりでいく。ウチは個人塾だから、売り上げが減っても上司に怒られることは無い。私が生活に困るだけだ。でもその分私の舌戦は本気だよ。
生徒指導は、本当にはじめが肝心だ。これを1度でも許してしまえば、私もその子にとって今までの大人と同じになってしまう。塾が生徒を預かるのってそんな無責任じゃダメだよね。はじめは痛みを感じるかも知れないけれど、絶対にその悪癖を強制してやるって思いで接する。本当に辞めちゃうこともあるけれど。
長文を「訳せる」のと「分かる」のは違う

生徒の勉強を見ていて思う。「訳せる」のと「理解できる」のはどうやら違うようだ。
英語でも古文でも、文章を訳すことはできるのだが、
「じゃあどんな話だった?」
と聞くと答えられない子が結構いる。もちろん訳すことに手いっぱいで内容把握に手が回っていないときもあるけれど、いざ訳された文が何を言っているのか分からない、なんてことがある。自分で訳していてもね。 昔の翻訳サイトのように、ただ単語を置き換えるだけになってしまっている。
だから、文章のテーマを知らないようならその内容をかいつまんで説明したり、訳文を理解できていないのならば理解できる言葉や言い回しで言い直したりすることがある。「和訳をさらに『生徒向けに訳す』」というなんとも不思議な作業だ。
これを解消するには、生徒の語彙力や読書の経験値を増やすしかない。たぶんここに「勉強の内容だけを教わっても伸びない」という原因のひとつが隠れていると思う。
止まらないで

授業の演習中に止まってはいけない。これがウチの塾の暗黙の了解だ。
生徒の学力はいつ伸びる?と問われれば、「自分で伸ばしている時」と答える。授業を聞いたときでも、内容を理解したときでもない。それを「自分のモノ」にするために書いて覚えたり問題を解いたりした時だ。
だからもくせい塾の授業は演習中心である。その時間に立ち止まるのは、自分を伸ばす作業をしていないことになる。だからそういう場合は立ち止まらないよう促す。
これは、手を止めて考えている時を指すのではない。考えている時は頭を動かしているのでOKだ。目の前の作業から目を離し、シャーペンを分解し出したりする子に対して行う。私は全員を見ることができる位置にいるのでよく分かる。頭を働かせることを怠っていたらすぐに言う。そういう意味ではサボれない塾だ。
こういう子はだいたい、分からない問題にぶつかると意識が逸れる傾向がある。だからその時の対処法も指導している。
「分からなければ持っておいで」
「分からなければテキスト使って調べていいよ」
もくせい塾では、授業中に立ち歩きが多い。生徒たちは自ら辞書や参考書を取りに行くのだ。それをせず、かといって質問もせず、ただ声を掛けてもらうのを待っている子には、「止まるな」という声がかかる。そういう意味では厳しい塾だ。
でも勉強って、「自分で取りに行った」ときに身に付くものなんだよね。やりかたは全部教える。でも私が代わりにやってあげることはない。
今スグ勉強はじめられる?

勉強のポイントは、
「どれだけ触れやすくしておくか」
だ。すぐにでも始められる環境なほど、学習に触れる機会が増えて効果も高まる。だから自宅の机の上は整理整頓した上で、テキストなどを「開いたまま」置いておくことをおススメする。朝起きたらすぐに見えるように。勉強の前に机を片付けなくてはいけない状態だと、よっぽどのことが無い限り勉強をすることはない。
それと同じ理屈で、単語カードなどを制服のポケットに忍ばせておくことも良い。自分で単語を書いておいてもいいし、それすら作るのが面倒ならばすでにカードになっているものが売っている。私も中学生の時、手のひらサイズのメモ帳を単語帳にしてポケットに入れていた。それほど使うことがなくてもポケットに入っているだけでなんとなく開いて見てしまう。この「なんとなく」の時間に触れるのが大切だ。
実際に学習するまでの敷居を、限りなく低くしていくことが勉強ができるようになるコツだ。
分詞の学習に入った中2

中2のある子が、英語で分詞の修飾のところを進めている。学校では中3の2学期に習う範囲だ。ペースは結構早い。
この範囲の学習では、修飾というのがポイントになる。日本語とは異なる語順や、被修飾語の文中の成分は何なのか。そういったところまで理解できるようになってほしい。なぜなら、ここから英語の文と言うのはどんどん長くなるからだ。修飾ってのは付けたしだからね。骨組みだけだった文に飾りがどんどんくっついてくる。本格的な英文読解の入り口に立った。
そしてここを乗り越えられれば、この先の英語読解はそれこそ大学受験レベルまでスムーズになる。非常に大切な所なのだ。早目に英語学習を完成させて、受験勉強を有利に進めさせてあげたい。
次へのスタートはもう切っている

新高1の子。高校の学習を進めている。
まだ高校からの課題も出ていないので自分で教材を用意して勉強を始めたのだけれど、数学は展開・因数分解を終えて根号の計算を進めている。塾の授業がちょっと追いつかないくらいだ。私もメッチャ本気出して説明してる。そして英語は渡した単語帳を進めている。もう300語くらい覚えたかな?あと高校生用の英語長文を読み進めてる。いいね。
高校生活は中学のときのそれと比べてペースが速い。ゴールデンウィーク明けに中間テストがあると思うけれど、その時に「さて、勉強すっか」では完全に乗り遅れる。もうレースは始まってる、今からリードしておくことが身を助けるのだ。
塾では間違えてね

小学生だった頃の記憶。
クラスメイトの男の子が授業で発言して、それが間違っていた。それで先生だったか、クラスのみんなだったかに
「違います」
ということを言われて、その子が泣き出しちゃったことがあった。小学校低学年か中学年くらいの話。今考えると泣くほどのことじゃ全然ないんだけれど、なんとなく「間違ってはいけない」的な空気があったのかも知れないね。もしかしたら記憶にないけれど私も同じ状況で泣いたことあるかも知れない。
時は流れて今、私は塾講師なんてものをやっているけれど、生徒は間違える。とにかく間違えまくる。それに対し私はいじる。いじりまくる。生徒はそれを聞いてケラッケラ笑う。
「ちょっと恥ずかしいけれど、楽しい」
くらいがちょうどいいだろうと思ってやっている。おかげで私の「レシーブ力」はとんでもないことになっているはずだ。全部拾うからね。
でもその時に気を付けているのが、上で書いたみたいな「生徒が悪い」という雰囲気にならないようにすること。オモシロの部分は生徒のパーソナリティに触れることではなく、こちらで用意したファンタジーにすることだ。生徒が安心して間違えられる環境ってかなり大切だと思う。
「スキマ時間」に勉強をするのは難しい

よく言われる
「スキマ時間を使って勉強」
というやつ。これ結構難しいよ、私はできないもの。でも世の中の大人は子供に対して言ってしまいがち。
「時間が無いなら、スキマ時間を使って勉強したらいいじゃん」
って。実際それは正しいし時間が無い子はそうするしかないのだけれど、果たして「たいして興味のない」勉強に対してそれができるかどうかは、また別問題だ。
確かに世の中にはそれができる子もいる。勉強に強い動機があって、スマホよりも鉛筆を先に手に取れる子。こういう子は放っておいても勉強するので、スキマ時間に勉強だってできる。でもそれ以外の大多数の子はそうじゃない。
考えてみてほしい。自分が今の生活に加えて、「スキマ時間の勉強」をしなくちゃいけないと言われたとする。それも自分の興味が持てない分野、そうだな「レメリグ語を覚える」とかを申し付けられたら。まあ続かないよね。強い動機がないと大人でもなかなか難しいことだと思うのね。
だからこのアドバイスは「言うは易し...」なのだ。本気で子供に勉強をさせたいと思うのならば、そのスキマ時間しか勉強できない状況をなんとかして整理してあげるしかない。「スキマ時間に~」は、「瓶の中に小石を入れてから大きな石を入れる」ようなもの。なかなか無茶なこと言ってるよ。子供に遊びの時間をゼロにしろって言ってるようなものだもの。
高校も卒業式か

そろそろ卒業式シーズンだ。高校ではもう行われたところもあるみたいだいね。卒業生のみなさまおめでとうございます。
大学に進学する人は、どんな生活をするかイメージしておくといいと思う。高校の時よりも更に世界が広がる体験になるだろうから、家と学校の往復だけじゃもったいない。自分の自由に使える時間も増えるから、それを有意義に使っていきたいよね。大学以外のコミュニティも広がるチャンスだ。もちろん自由度が上がるということは、それに伴って責任も大きくなるけれどね。世間からはもう子ども扱いされないので、それにふさわしくありたいよね。楽しんでよく生きてください。
13年

東日本大震災から13年が経った。
ということは現在小6の子たちはリアルタイムではないのね。もちろん情報として、映像などは見ているだろうけれど、時が過ぎるのは早い。
私はあの日も塾講師として働いていた。ものすごい揺れを感じたあと、教室を出てみたら電線が尋常じゃないほど揺れていた。
それから数年し、復興が進んだ東北へ旅行へ行った。女川、気仙沼などを車で回る途中、新たに整備された道路には「ここまで津波が来た」ことを知らせる線が引かれていた。みんな私の背丈よりもすっと高い位置だった。
最近の教科書は、テーマに災害が盛り込まれている。それを、実際に知らない子たちに伝える責任の重みは感じ続けたいよね。
勉強は単純作業ではダメだよ

もくせい塾は自習ありきの塾た。イメージは、生徒が1週間自学で勉強をしていって、その途中に授業があるって感じ。
だからそのイメージ通りになっている子は成績がガンガン伸びるし、「授業の時しか顔を見ないな」という子はビミョーになる。入塾時に「ウチは自習に来ることをお願いしています」と言っているのはすでにその経験則が塾にあるからだ。中学生の「自宅で勉強しています」っていうのは、せいぜい定期テスト止まりなのよ。
ただし、塾に自習に来ていてもビミョーになってしまう子というのもいて、それは「時間が来たら帰っちゃう子」だ。何か用事があってその時間までしかいられないというのではなく、いつ来ても同じ時間に帰る。そういう子は塾に来ても、ただいるだけなので成績が上がらない。
大人なら分かると思うが、いつでも同じ時間に終わる仕事なんてあまりない。時間がきたらやむを得ず切り上げるか、終わるまで残業するか。時間ぴったりに終わるのは、単純作業の仕事くらいじゃないかしら。
だから自分で帰る時間を決めてしまっている子は、時間が来たら帰れると思ってしまって勉強の密度を高める工夫もできない。よって学習効果も低く成績が上がらない。学習記録シートを書かせているのは、勉強を時間ではなく量で考えさせるためなのだ。
積み残しのないように
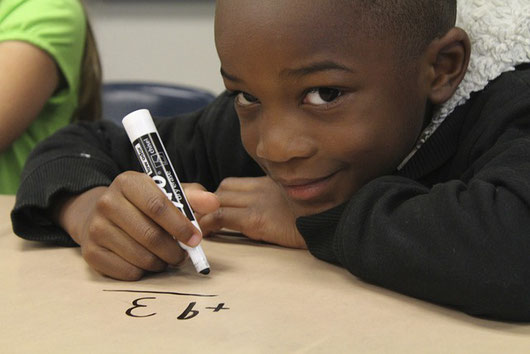
昨日は自習に来ている子が多かった。
中学生は今、返却されたばかりの期末テストの直しも含めて、今学年の復習を行っている子が多い。中学校の数学は、1年を通じて計算・方程式、関数、図形、資料の活用の分野を学ぶ。ここまでくると中学数学の全体像が見えてきたんじゃないかな。自分の得意・不得意もなんとなく見えてきた頃だろうし、苦手をピンポイントで補うこともできるはずだ。次の学年に上がっても、また同じ分野をもう1周する感じになる。(内容はもちろん変わり、難しくなるよ)ここで積み残しを無くしておくことが、学年が上がった時にテストの点数を下げないポイントだ。
エネルギーの割り振り方を変えよう

勉強を「後回し」にしてしまうとうまくいかない。もし本気で成績を上げたいのなら、その順番を前にするだけで効果が出る。
私自身の体験だが、学生時代の勉強をしなくてはいけない立場に追い込まれた時に、つい「後回し」にしてしまっていた。
「学校がある時間は自分の勉強はできないよな」
「授業が終わったら部活だから」
帰宅しても、
「塾までに食事と、その後は疲れてるからちょっと寝てから行こう」
「塾から帰ってきたばかりだし、少し休憩。テレビ見よっと」
「お風呂入らなきゃ」
そして、「今日は疲れたし、もう寝よう」と。人にはエネルギーの総量がある。こうなってしまうのは仕方のないことなのだ。(自分に甘すぎ?)
もし勉強しなくちゃいけないと思いつつ、なかなか行動に移れていないのならば、自分のエネルギーが残っている時間帯にやるべきだ。食事前とか、学校終わりにいろいろ予定のある人ならば朝とかね。やることの順番を入れ替えるだけでだいぶ変わるはずだ。
よーいドン!

中2の中には少しずつ変化が見られるようになってきている。「進路」への意識の変化だね。
志望校の話をする子もいれば、「勉強をもっと頑張らなきゃ」と危機感が出てきた子もいる。いずれにせよ良い傾向だね。ほとんど全ての子たちがこれから受験を迎える。受験勉強のスタートは早いほど可能性が大きくなる。
そしてスタートの合図を出すのは他の誰でもなく、自分自身だ。意識が変わることで、その号令を早めることができる。受験勉強にフライングは無い。
ゲーム感覚

昔から
「今年は〇勝△敗だ」
という言葉が大っ嫌いだ。生徒の受験結果をこのように表現する塾関係者の多いこと。人の人生を数字に換算する、どこか他人事な物言い。
「なに『敗け』って。あなたが勝負したの?」
って思っていた。そういう講師に限って、受験生がどこを受けたのかを全部把握していなかったりする。生徒と一緒に這いつくばって泥水を啜り、七転八倒した経験がないのだろう。その経験があったら、そんな言い方はできないよね。
公立高校の欠員募集

埼玉県立高校入試の欠員補充の情報が出ている。
このあたりの全日制高校でも、春日部工業や川口青陵などが募集をしているみたいだね。
この「欠員」という言葉の響き、なんかちょっと嫌だなと感じるのは私だけかしら。2次募集とかのほうが聞こえが良い気がするのだけれど。いろんな理由でこの試験を受けることになった子だっているんだから。
小学生が模範となる日

小学生たちの学習姿勢がどんどん良くなっている。
まず文字。適度な筆圧が出てきた。それによって、漢字テストの合格率が上がっている。また、自分の文字の見間違いも減った。
そして計算問題のミスが減っている。聞くと、
「ゆっくり解いた」
とのこと。取り組み方が丁寧になってきた。そして質問。分からないところをちゃんとしばらく考えてから、自ら質問に来ることができている。解いた問題を見せるときも、どこがどう間違ったのかを自分で説明できている。英語の問題を解くときに、間違えた単語はその場ですぐに覚えるようにしているのもいいね。
こういうのって年齢じゃないんだね。小学生でもこうなれる。
古本を探して

今日は朝からブックオフを回った。欲しい過去問があったんだよね。少し古いやつ。
越谷店、せんげん台店、春日部(豊春)店…在庫なし。仕方がないので三郷店に行ってみたけれど無し。東川口店も無し。
んで、草加店でやっと見つけた。灯台下暗しとはこのことか。6件も回っちゃったよ。古本は確実に置いてあるわけじゃないのでこういうこともあるね。
模倣力

お手本を守れる子は伸びる。
例えば計算問題を教える時、
「このように解くんだよ」
ということを指導する。途中式を必ず書くんだよ。途中式の等号は縦に揃えて書くんだよ。約分は分母と分子の数にナナメ線を入れて行うんだよ。
そういったことをいつまでも守っている子は成績が良い傾向にある。一方成績の悪い子はそういった教えを破るのも人一倍早い。
「先生のやった通りに真似っこしてやってごらん」
と言った直後にオリジナリティを出してくることもままある。ルールは守るものだという意識と、模倣する技術が足りていないのだろう。お手本はやがて超えていくべきものだが、それよりも質の低いオリジナルでは意味がない。
勉強ができる子に育てるには、勉強自体を教えるよりも先に、この部分を教える必要がある。勉強の「周辺」の力のひとつだ。
さあ、頑張っていこうや。

「成績を上げたい」と言って入塾してくれた高校生。
まずはリサーチからはじめる。
それまでの勉強の話を聞いてみる。何をどれだけやってきたのか、高校受験の時はどう過ごしてきたのか。目標は、今後どうしていきたいのか。
その中で改善点と塾でやるべきことを具体的に話した。全部で1時間くらいかな。話だけで疲が見えていたのを見逃さない。頭を働かせるように質問していたから。勉強体力も付ける必要があるね。
勉強のやり方は分かってるけれど、それができていないと本人も気付いている模様。それができる環境を用意してあげるつもりだ。また、話す内容や話し方から見えてきたことも踏まえて指導に活かしていく。大丈夫、変われるよ。
そのままじゃやばいよ
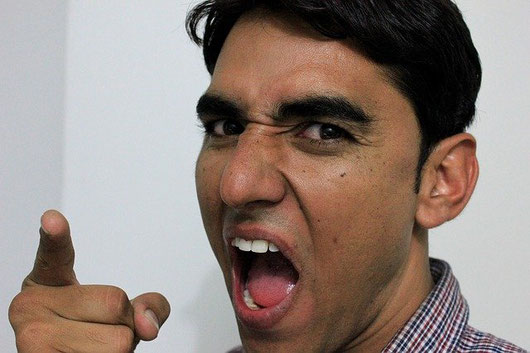
やばいね。
学習した内容が抜けまくっている生徒がいる。
定期テスト後に自習に来なくなった生徒たち。1年間の総復習をさせてみたら、んまぁ~できなくなっている。テスト前だけ詰め込んでお茶を濁しているとこうなってしまう。
同じ内容を何度も教えるのが「甘やかしすぎたかな」と思ったので、今日は少し突き放してみた。
「以前やったことだから、自分で正解してごらん」
と。勉強は自分でできるようにならないと意味がないんだよ。そして受験ではその力が試されるんだよ。いつまでも甘えんぼさんではいられないのだよ。
できないことは仕方のないことだけれど、期末テスト後の塾の小テストが準備不足で不合格してしまったり、返却された答案をすぐに持って来なかったりするはさすがによろしくないと思うな。そういう意識が変わらないと結果はついて来ない。
もくせい塾が今の形になったワケ
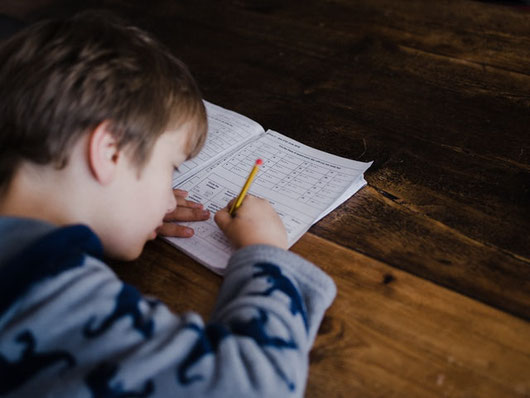
生徒に冗談で言っていたことがある。
「私の理想の塾は、自分が死んで立てたお墓の周りに生徒が集まって、勝手に勉強して成績が上がることだ」
これは別に、「ラクをしたい」ということではない。
昔、自分の説明技術を磨けば磨くほど生徒の成績が伸びなくなったことがある。塾講師を始めたばかりの頃のほうが生徒は伸びていた。じゃあ何がいけなかったのかを考えた時、「自分が先回りして教えてしまっている」ことに気付いた。生徒がつまづきそうになったらすぐに助け船を出す。生徒が分からなそうなところはあらかじめ説明してしまう。そうした舗装された道路を歩くばかりでは成績は上がらない。
勉強は、教わっただけでできるようになるものではない。その後に自分でやってみて、身に付けてはじめてできるようになる。だから、講師の説明は必要最小限にし、生徒が自分で試行錯誤する環境を用意する。生徒をラクさせてはいけない。そう思って自学力を育てる塾という考えに辿り着いた。
生徒が主役の授業を
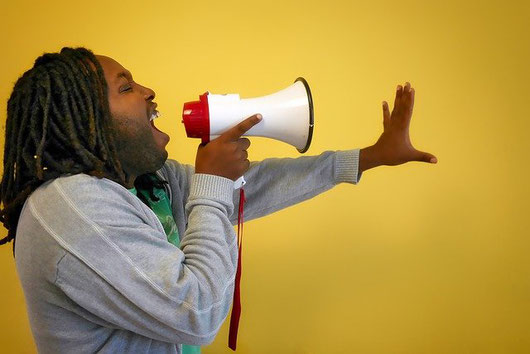
昔働いていた個別指導塾で、講師を見ていて感じたこと。
「生徒を伸ばす講師は『生徒を主役にする』のが上手い」
上手い講師ほど個別指導では自分をサッと引かせることができる。生徒が自分の手で行う作業をきちんと残す。主役として生徒が一番歌って踊れる場面を作る。
反対に生徒を伸ばすのが下手っぴな講師は自分が主役に躍り出て高らかに歌い上げちゃう。授業中ずっと説明してるんだよね。話を聞いている生徒もそれで疲れちゃってる。こんな授業は意味なし。やっぱり塾講師は「サービス業」。自分が気持ち良くなってちゃダメだよね。生徒を疲れさせるなら、頭を使うことで疲れさせなきゃ。
体調不良が多い

季節の変わり目ということもあり、生徒の体調不良がまた多くなってきた。気温の寒暖が大きいからね。
学校から帰ってきたら必ず手洗いうがいをしましょう。学校では、風邪やインフルを必ずもらうものと考えて、それを防ぐ意識を持ちましょう。保護者の方にもご協力をよろしくお願いいたします。
簡単な「予習」のススメ

あと1ヵ月で新学期だ。
新学年に入る前に準備としてやっておいてほしいのは、次の学習内容を「知る」ことだ。
教科書があるならば教科書の、目次や見出しだけでもパラパラと見ておく。教科書が無いのなら問題集でもいい(塾の本棚にはどちらもあるよ)。具体的に勉強をはじめなくてもいい。こうして知っておくだけでも授業が始まってからが全然違うのだ。
自分が学習する全体像を知っておくことで勉強の方針だけでなく、ペースや強度の見通しが立ちやすくなる。定期テストの勉強でワークを何周もするときに、はじめの1周目は時間をかけずにやるのも同じ理由だ。ゴールの見えないマラソンをするのはキツい。どこまで走るかが分かると安心できるし、「知っている」ということが授業への興味にもつながる。おススメ。
本当にそれ、個別で見れてる?

最近、
「『個別指導』で伸びない原因はコレかなぁ...」
って思うことがある。「『個別指導』なのに、指導内容が生徒に寄り添っていない」だ。
もちろんね、「生徒本人の勉強量が足りていない」が一番の理由だよ?そこは絶対そう。でも、個別なのに先生の都合で進んでいる指導ってかなり多いんじゃないかなと思う。例えば「テストまでに範囲を終らせなきゃいけない」っていう塾側の理由とかで。生徒ができるようになっていようがいまいが、とにかく先に進んじゃう。まあ生徒は伸びないよね。
というかこれだと集団塾と同じだと思う。カリキュラムがまずあって、それを受けたらあとは生徒の裁量次第ってやり方。子供を個別指導塾に通わせる保護者の方ってこれを望んでいるのかなぁ。少しでも学校のテストの順位を伸ばしたい、それこそ「範囲は終わらなくてもいいので、できるところを増やしてあげてほしい」って思っている保護者の方とかいないかな。
もくせい塾は個別指導塾じゃないので関係のない話だけれど、生徒を「個人」として見るということを追求しているのはたぶん同じなので気になったのよね。
受験に間に合うには

埼玉県の高校入試は、1月の後半に私立高校、2月の後半に県立高校入試が行われる。
そこで受験勉強という観点で考えると、どんなに遅くとも年内に中3の範囲を終わらせておきたい。そうでないと、入試の過去問を解く時に「まだ知らない」問題があることになる。特に埼玉県立入試の数学では、中3の後半に習う内容が絡む出題も多い。
しかし公立の中学校では年内に範囲が終わっていないこともままある。2学期の期末テスト(11月中~後半に実施)の範囲を見てみると、「まだ半分くらいしか終わってないじゃん!」ってこともよくあるのだ。もちろん公立中学校は受験のために授業をしているわけでは無いので仕方ない。しかし中学校の授業だけで受験をするとなるとこの点はやや不利だ。
そこで塾では予習型の指導で進めておきたい。いつまでも「学校の進度に合わせて指導します」だと、受験で戦う力を養う時間があまり取れないことになる。このあたりは高校受験生の子を持つ保護者の方にも知っておいてほしいことだよね。
北辰、からの~受験生!

昨日は中1・中2の北辰テストだった。
中2はここから受験生として扱っていきたいと思っている。中3生でなく高校受験生。やっぱり学力向上のためには意識が大切だよね。もちろん中3で習う内容を丁寧に勉強していくことは大切だけれど、それだけでは受験は乗り越えられない。中1・中2の内容の復習など、今からでおやれることはたくさんある。そしてそれに早く手を付けた子から受験は有利になっていく。いずれみんながやることだからね。
塾の授業では、すでに中3の範囲を進めている子もいる。1学期の期末テストの範囲がほぼ終わっていて、またテスト前には戻ってくるけれど、早目に中学生の学習内容を1周して受験までに重ね塗りを繰り返せるようにする。さあ、スタートだ。
受験指導はどうあるべきか

埼玉県立高校入試の合格発表日から1日経った。
塾の実績として「全員合格!」を謳おうと思えば、実はそう難しいことではない。受験生の志望校を安全圏まで下げてしまえばいいのだ。進路指導の面談で、
「ここは絶対に無理ですね。こちらを受けて下さい」
と言ってしまえばいい。実際にそういう進路指導をする塾もあるかも知れない。もちろんご家庭が合否にこだわるのなら、それは「親切な」アドバイスだ。しかし、行きたい学校があるのにそれを外野が諦めさせることが本当の受験指導だろうかとも思う。
このへんは実際に受験をする生徒、その保護者、そして塾の価値観の違いもあるだろう。でも私が思う本当の受験指導とは、もし合格可能性が低くてもその可能性をきちんと示し、「それでも目指しますか?」と問い、合格するために全て投げ打つ覚悟を決めて勉強をさせることだ。はじめから負け戦はさせない。
小学校の英語から中学校の英語へ

小6の子の中に、そろそろ中1の英語ワークが終わりそうな子が出てきた。
ここでまた一旦戻って、また中1の初めの文法から指導し直していく。中学生に入って英語で躓かないように基礎をしっかり固めるのだ。
英語は初めで分からなくなってしまうと、リカバリーしにくい科目だ。積み上げの教科だからね。分野ごとに学習できるものではなく、全部ひと続きの知識体系になっている。初っ端の動詞、いやそれ以前に英語の勉強の仕方が身に付いていないとやがて迎える高校入試で手も足も出なくなるし、その後高校の英語の授業もちんぷんかんぷんになってしまう。
だから本当にはじめが肝心。本当は小学校の英語授業もやらないでほしいと思っている。内容が依然として英会話のままなので、そのままだと中学に入ってからの学習で対応できないし、そもそもフレーズを覚えるだけになってしまいがちだ。興味を持てる子ならいいのだがそうでない子は覚える作業をきちんとやらないと全くついていけない。あそこで英語嫌いが結構発生している気がする。
だから塾ではここでゼロから勉強をし直していく。小学校の英語学習の禊をする。本格的な英語学習のイニシエーションだ。
明日北辰テストを受ける生徒へ
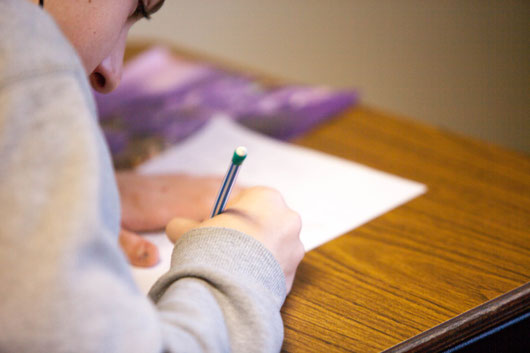
明日は中1・中2の北辰テストだ。
もくせい塾からも受験する生徒がいるけれど、ここまで積み上げた学力の確認をするために受ける子も多いんじゃないかな。特に中2の生徒にとっては3年生になる前に一度自分の学習を振り返るための大切なテストになる。ここから「受験生」になる子も出てくるはずだ。
そんなわけで昨日は授業を受けた子たちに北辰テストの話をして問題を解いてもらった。はじめて受ける子もいるのでどのようなテストなのか、レベルはどんなものか体感することができたのではないだろうか。
北辰テストは埼玉県立高校入試の模試だ。実際の入試問題に形式を似せて作られている。なので北辰テストを受けていくことが入試対策にもなる。学校のワークと教科書、北辰テストだけでも公立入試の勉強は十分にできると思う。それこそ外部の会場に試験を「受けに行く」ということ自体がすでに経験値だ。
しかしただ受けるだけでは効果は出ない。受けた後が大切だ。当日問題に自分の解答を書いておき、帰ったらまず自己採点を行ってみよう。そして配られた解答を使ってしっかり解き直しをすること。その時に学校のワークと教科書を連動させることが効果的な勉強につながる。高い受験料を支払うのだから、目一杯活用してほしい。
公立中の定期テストの得点分布

上のグラフを見てほしい。ある中学校の今年度実施された定期テスト5教科の得点分布だ。
見事に「ふたこぶラクダ」の形。最も低い0~49点のところが盛り上がっている。ここに属する子は定期テストで1教科平均10点も取れていない。

次は英語のみの得点分布。
これは衝撃的だった。最も多いのが30点未満の成績だなんて。平均点は52点でやや低いけれど、問題はごく標準的なもの。これが今の公立中学校の現実だ。
英語の学習指導要綱が悪いのかと思ったが、他の科目でもここまで極端ではないけれどこんな感じ。勉強しない子は今後も増えていくのだろう。これを見て、子供の幸せのために学問を身に付けさせたい親はどう思うのだろうか。
北辰対策について

入塾面談で
「北辰テスト対策はやってくれますか?」
と聞かれることがある。高校受験生の保護者の方ね。北辰偏差値で私立高校受験を考えていらっしゃるのだろう。
北辰テストの問題に触れて解説とか、出題についてあれこれ言うことはできる。でもこれが受けた北辰テストの結果を上昇させるかと言うとなんとも言えない。本当の意味での北辰テストの対策は、受験勉強をするしかないからだ。北辰テスト自体が県立入試問題の模試だからね。
だから受験対策を行って受験勉強をしていけば、北辰テストの成績も伸びる。もくせい塾では受験生の北辰テストの成績は夏以降で大きく変わってくる。夏期講習で受験勉強をさせるからね。私はこれも北辰テスト対策だということにして、上の質問に対し
「はい、やってますよ」
と言っている。いわゆる、「北辰テスト対策講座」みたいなのはやらない。そもそも受験がまずあって、その対策として北辰テストを受ける。その北辰テストを受験のために「対策」するのは本末転倒だろう。
とはいえ、保護者の方にとっては受験に対し差し迫った悩みでもあるだろう。だからこそブレずに受験対策をしていき結果を出す。お金だけ取られてちまちまとやる講座よりもきちんと効果は出まっせ。
高く飛べたね。よし、じゃあ次行こうぜ。

今日は朝から気持ちが揺れ動きすぎて、今ちょっとぐったりしている。ダメだよね、普段「結果に一喜一憂するな」なんて言っているくせにね。
そんなわけで、ちょっとピリッとしたことを書いて自分を律したいと思う。新高校1年生にアドバイスだ。
高校の学力のトップ5くらいの生徒は、どこの学校でも超優秀だ。偏差値50の学校でも70の学校でもね。そうなる生徒はもう次の明確な目標があって、合格発表のあった今日もすでに勉強を始めていたりする。もうとっくに高校生やっちゃってるのよ。どう?怖くない?
高校が決まって、入学式の日まで、中にはゴールデンウィークが明けるくらいまで合格の喜びに浸ったままピヨピヨと何も考えずに過ごしてしまうと、高校の勉強の「後発組」の仲間入りをすることになる。同じ試験で入学したのに、もう簡単には抜けない人が前にズラッといる状態。
今回の受験で勉強の厳しさを感じたのなら、「あと少し早く始めていれば」を感じたのならば、もう次に向けて進むべきだ。「できないやつ」というのは、高校受験で不合格になった人のことを言うのではない。同じ過ちを繰り返してしまう人のことを言うのだ。反対に、高校受験で合格したからと言って何かが保証されたわけではない。
縁

「縁は異なもの味なもの」と言うが、これは男女の仲だけでなく受験に関しても言えることだ。受験では本当に何があるか分からない。倍率や偏差値、合格可能性というのはつくづくただの数字であって、本当に呼ばれた学校に通うことになるんだなぁと思う。
今までに縁について考えさせられた受験の思い出はいくつもある。それまで、滑り止め校も含めて全て不合格だったのに最後の最後に受けた第一志望の大学だけポーンと受かってしまった子や、高校では本人が望まない所に進学したけれど、その後発奮して勉強し、誰もが羨むような大学に合格した子もいた。
こんなこと、受験指導を生業にする塾講師が言うべきじゃないかも知れないけれど、通うことになった学校と「縁」があったと思えることが大切なのだと思う。
埼玉県立高校の合格発表日

埼玉県立高校の合格発表日だ。
結論からいうと、全員合格だった。ただ、素直に嬉しいという気持ちよりも、驚きのほうが勝っていてなんかもう気持ちもグチャグチャだ。さっきからイスに座ったりまた立ち上がったりを繰り返している。せっかく報告に来てくれた生徒にも、ロクにまとまった祝辞も言えずにゴニョゴニョしてしまった。
今回は全くもって大逆転劇だった。1・2年の通知表が6ポイントも低かったら普通は無理だよね。学校の先生にも「過去にこの成績で合格した人はいない」と言われていたし、前例を作ったことになる。申し訳ないが正直、不合格の報告を想像していてそのための心構えをしてしまっていた。
舞い上がっている気持ちもいい加減見苦しいのでこのくらいで抑えるとして。
合格した生徒のみなさんへ。良かったですね、ほっとしました。今回の合格はひとえに君たちが夏休みから必死に努力してきた結果です。塾の課題に真面目に取り組み、ひたむきに頑張ってきたことをずっと見てきました。正直結果がどうであれ、私が最後まで諦めなかった君たちのことを誇りに思う気持ちは変わりません。
しかし、東部地区の高校の中では高倍率を争ったという事実の裏には、残念ながらあと一歩届かなかった生徒もいるということにも目を向けてください。努力の量も、高校への想いも、そういう子たちが自分より劣っているというわけでは決してなかったはずです。きっと、ちょっとした運だけなのでしょう。だからそういう人たちの分も頑張っていって下さい。これからも私と一緒に勉強していく人も、そうでない人も、高校では「自分が最下位」のスタートです。その気持ちで前を向いて進んでいってください。
合格おめでとうございました。
